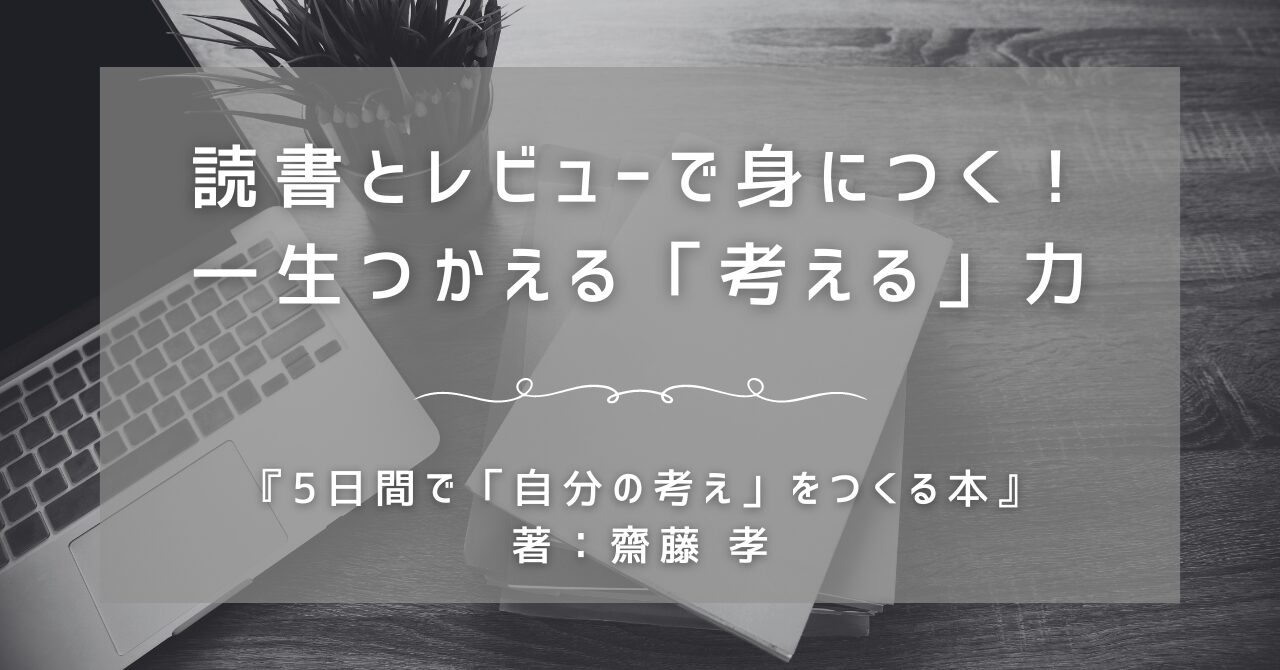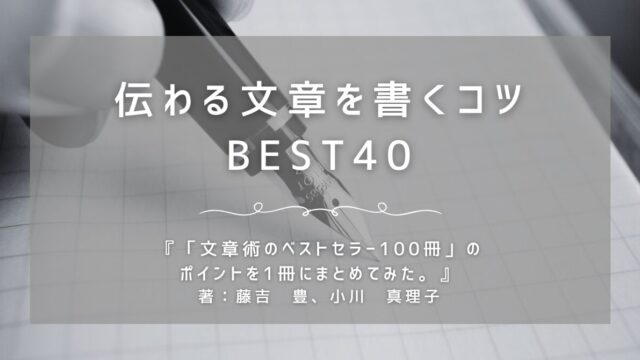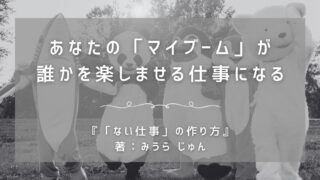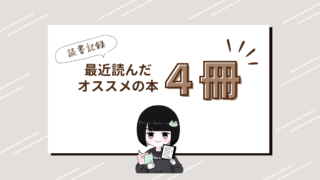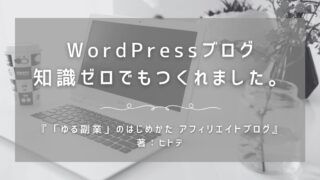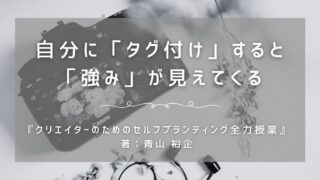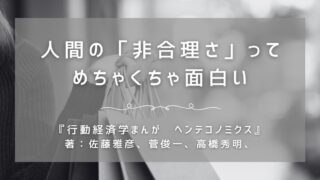今回はこちらの本をご紹介します。
| タイトル | 5日間で「自分の考え」をつくる本 |
| 著者 | 齋藤 孝 |
| 出版社 | PHP研究所 |
| 初版発行日 | 2014/7/8 |
| 備考 | 紙の本で読了 |
単なる話術やライティングの本ではなく、人生が豊かになる思考の訓練法です!
- 「自分の考え」や意見を聞かれるのが苦手
- 自分なりの感想やレビューを書くコツが知りたい
- 読書でアイディアや話の引き出しを増やしたい
どんな本?
ある新聞記事を見せられ、「どう思う?」と尋ねられたとしよう。あなたは即座に気のきいた回答をする自信があるだろうか。
「1日目」の出だしから、ドキっとさせられる質問です。
もちろん内容によるところもありますが、私はぶっちゃけ自信がありません(笑)
みなさんはどうでしょうか。
自分の考えや意見を持ち、それをアウトプットする能力は、今後ますます重要になってくると思います。
情報量や知識量については、(よほど特殊な人や分野でもない限り)ネットやAIと張り合っても勝てません。
だからこそ、目の前の情報に対して何を考えるか、考えたうえでどう行動するか(伝えるか)が、重要になってくるわけです。
しかしこういった能力は、暗記や受験対策が重要視される学校教育では、なかなか身に付きづらい部分ですよね。
本書の最終目標は、そういった能力を身に付け、実際に(意思決定をして)行動に移せるようになること。
具体的には以下のステップに分けて、5日間で身につくように解説されています。
1日目にブログやSNS、ネット上に書評を書いて勘を養い、
2日目に偉大な先人たちが生み出した思考パターンを学び、
3日目に生活習慣を見直すことで「考える体質」をつくり、
4日目に読書によって素養と話題を味方につけ、
5日目に満を持して「意思決定」に挑む。
インプット、アウトプット、思考、習慣…各ステップがそれぞれ相乗効果を生んで、「自分の考え」が言えるようになる!
著者の齋藤孝さんは、明治大学文学部教授であり、身体論や教育、ことばに関わる数々のベストセラーを執筆してきた方。
NHK Eテレの『にほんごであそぼ』では、総合指導も務めています。
そんな「ことばと教育のプロ」が、10年前に書いたのがこの本。
どんなに時代が変化しても、「考える力」は普遍的なスキルであるということが、よくわかる一冊です。
全体の感想
ざっくり感想
本書はタイトルに「5日間で」と書かれていますが、現実的に考えて、5日間で完璧にマスターできる!という内容ではないと思います。
というか、一度読んだだけですべてを理解して実行するのは、正直難しいです。
しかし、多くの実践的なノウハウから日常のなかで意識すべき「考え方のコツ」まで、そのひとつひとつにとても説得力があり、取り入れたくなるものばかり。
ステップに沿ってやっていくのも良いですが、たとえば「ブログでレビューを書く」と「読書習慣を持つ」というメインの行動を決めて、そこに自分が重要だと思った考え方やアドバイスをピックアップして取り入れていく…という使い方も良いかもしれません。
「ベストセラーを読んだら、気に入った言葉をピックアップして人に話してみよう」とか、「語彙力を増やすために、好きな芸人さんのラジオを聞いて、感想を書いてみよう」とか。
いっぺんには行動できなくても、いくつか自分なりに取り入れてみるだけで、少しずつ「自分の考え」をつくる力が鍛えられるんじゃないでしょうか。
ストレスを感じたら「体を温める」など、身体と考え方とのつながりについても触れていて、こちらも実践しやすそうです(トランポリンがある会社、羨ましい~)。
齋藤さんの本は、知的好奇心や学ぶモチベーションを上げてくれる本が多く、定期的に読みたくなります(著書の数が多すぎるので、まだまだ気になる本がいっぱいです)。
本のなかでは毎回多くの引用や著名人のエピソードなどが出てきて、その知識量と引き出しの多さには、毎度圧倒されてしまいます。
ふだんあまり本を読まない方からすると、情報量も多く少し難しい印象を受けるかもしれません。
ですが、そういった本を読んでみること自体、知らないことばや作品と出会って、語彙を増やすいいきっかけにもなると思っています。
誰でもできる!まずはレビューを書くことから
1日目の具体的行動として紹介されているのが、ネット上でレビューを書くこと。
自分の好きな本や映画、音楽など、まずは身近なもののレビューを書いてみることをおすすめしています。
とはいえ、「いきなりレビューなんて難しそう…」と思う方もいるかもしれません。
しかし、本書では基本的なレビューの書き方のコツや、いくつかのパターンが紹介されています。
その中でも、私がとくにポイントだと思った部分をいくつか抜粋してみました。
- 事実と情報(要約)が8割、自分の意見2割
- 自分のキャリア(立ち位置)を書く
- 悪口は避け、できるだけ褒める
- 一部分について限定して書いても◎
- 気に入った部分を「引用」してみる
※「自分のキャリア(立ち位置)を書く」は、「この監督の作品は全部見ている」、「舞台となる業界で働いていますが…」のように、どういった立ち位置からレビューしているかを明確にすることで、説得力や信ぴょう性を持たせるということです。
1からすべて自分で考えたことを書くのではなく、これらの型や方向性を意識するだけでも、レビューを書くハードルが下がるんじゃないかなと思います。
ちなみに、商品の販売ページやレビューサイトに書くのもいいですが、個人的には(ネタバレがなければ)XなどのSNSだったり、noteやブログなどをレビューの場にするのもおすすめです。
SNSであれば、すでに好みの近い人とつながっていて、身近な人への布教に成功する可能性もあります(笑)
Xなどは文字数制限のネックがありますが、日常でつぶやく延長線上で、気軽に習慣化できるというメリットもあります。
私自身は、文字数を気にせず引用などもしやすいブログが良いなと思っています(そうして出来たのがこのブログですしね!)。
わざわざ来てもらえないと見られないデメリットもありますが、自分のコンテンツとしてストックできるのと、カテゴリ分けもできて見やすいのがメリットです。
『いいレビューは”社会貢献”だ』という言葉に、自分の意見としてレビューを書くことへの勇気をもらいました!
読書で思考の”粘り”を身につける
本書では、読書による効能が数えきれないほど出てきます(ちなみに4日目にあたる章は、まるまる読書術に関する内容です)。
齋藤さんは他にも読書に関する著書がたくさんありますし、先述のとおり、本書のなかにも多くの本からの引用や、幅広い分野の著名人のエピソードが出てきます。
けど、読書は単に知識を増やすというだけではなく、思考の”粘り”を身につけることができる、というメリットもあります。
考えてもすぐ飽きてしまったり、短絡的な結論を出してしまうのは、思考の”粘り”が足りないから。
もっと言えば、読む本の内容やボリュームに応じて、「脳の持久力」が鍛えられるという話でした。
これは、自分にはあまりない視点でしたね。
脳の持久力を鍛えるというポジティブな目的で、ちょっと苦手意識のあった古典や、ボリュームのある本に挑戦してみるのもいいかもしれません!
個人的アクションプラン
最後に、本書を読んでいて、個人的に「やってみたい」と思ったことを3つ選んでみました。
- 精神論や抽象表現は避けよ
- 「概念」からアイディアを釣り上げる
- 読書+実体験で小ネタをつくる
精神論や抽象表現は避けよ
これはちょっと耳が痛いです(笑)
なるべく「良かった」、「面白かった」で終わらないようにと意識してはいますが、代わりに「わくわくする」とかフワっとした表現を多用しがち…。
誤魔化しているつもりはないとはいえ、より具体的な言葉で伝えられるよう、語彙力を鍛えていきたいです。
「概念」からアイディアを釣り上げる
アイディアをゼロから考えるのではなく、ある「概念」と自分の記憶を結び付けて、そこからアイディアを引き出す…という思考法。
例えば本書では、棋士の羽生善治さんの本『捨てる力』が例に紹介されています。
この『捨てる力』というタイトル(概念)に注目して世の中を見てみると、よけいな機能や常識をそぎ落として上手くいった例が、意外と多いことに気付けます(録音機能を捨て、持ち運びを可能にしたソニーのウォークマンなど)。
そこから「じゃあ、この概念を自分がかかわるものに活かせないか?」と考えるのが、この思考法です。
「自分の考え」をつくるのはもちろん、クリエイティブなアイディアを生み出すのにも使える考え方ですね。
読書+実体験で小ネタをつくる
大学教授でもある齋藤さんは、講義で学生さんたちにさまざまなワークや課題を与えているエピソードが出てきます。
そのひとつが「15秒プレゼン」。
本を読んで気に入ったところをピックアップし、そこに自分の体験をワンセットにして、小ネタとして15秒以内で話すというものです。
これは「自分の考え」をつくるトレーニングにとてもよいし、単純に面白そうだなと思いました(人前でしゃべるのは苦手なので、自分が学生だったら辛かったかもしれないけどw)。
社会人でもプレゼンじゃなくても、こういった小ネタを考えて、文章でアウトプットするのもアリかもしれませんね!
まとめ
記録によると、私はこの本を、発売された2014年に購入したようです(Amazonにそう表示されているんですが、前のこと過ぎて中身の記憶も曖昧でした…)。
しかし今回読みなおしてみて、先述したように、「今から改めて参考にしたい!」「良い気付きになった!」と思える部分がたくさんありました。
冒頭でも言ったとおり、時代とともにツールや環境は大きく変化していますが、人間として必要な能力は、本質として変わらないものなのだと感じさせられます。
この本を買って読んだ(はず)の10年間で、自分がどれだけ成長できたのかを考えると目を背けたい気持ちになりますが、あきらめずにこれから出来ることを頑張っていきたいと思いました…。
とりあえず本のレビュー頑張るので、これからもよろしくです!(笑)